2015年は第二次世界大戦終結から70年という節目の年。しかし、ひとたび国外に目を向ければ、世界は今も紛争や暴力が絶えない。そうした現状を踏まえ、国際文化会館が国際交流基金とともにアジアの知的リーダーたちを日本に招へいする「Asia Leadership Fellow Program (ALFP)」では、世界的に活躍する写真家・石内都氏を招き、アジア共通の課題である「戦争の記憶」をアートの視点で語ってもらった。批評家・若松英輔氏によるコメント、ALFPフェローの意見とともにレポートする。
[2015年9月]

1947年生まれ。70年代から写真を撮り始め、街の気配や記憶、空気を捉えた初期の作品群で79年に女性初の木村伊兵衛賞を受賞。その後、自身の母の遺品を撮った「Mother’s」や、広島の被爆遺品を撮った「ひろしま」などを発表し、2014年には日本人として3人目となるハッセルブラッド国際写真賞受賞。近年にはメキシコを代表する女性画家フリーダ・カーロが遺した品々の撮影を手掛けたほか、米国初の個展が2015年10月~2016年2月21日まで、LAのJ・ポール・ゲティ美術館で開催されている。
石内都氏の「ひろしま」は、広島で原爆の犠牲となった人々の遺品を撮影したシリーズだ。撮影対象の多くは、人々が被爆の瞬間まで身に着けていた衣服。焼け焦げ、引きちぎられた洋服たちは、それだけで爆風や熱線の凄まじさを物語る。しかし石内氏がファインダーを通して見つめるのは、そうした凄惨な広島の姿ではない。水玉のブラウスや花柄のスカート、細かな刺しゅうや丁寧な継ぎ当て―主(あるじ)を失った衣服たちが語り出す人々の何気ない日常。その声にそっと寄り添うような深く温かな眼差しは、見る者の心にさまざまな思いを投げかけてくる。
1人の少女の死を見つめて
石内 都: 今日見ていただく「ひろしま」という作品ですが、原爆の遺品というとモノクロームでイメージされる方が多いかもしれません。私もそうでした。実際、これまでの写真の多くはモノクロームで撮影されてきました。 でも広島平和記念資料館に行って実物を見てみたら、ちゃんと色や模様があって、当時の若い女の子たちがおしゃれをしていたことがわかるんですよ。「資料としての遺品」ではなく、普通の女の子たちがいつもと変わらない生活を送っていたのを目の前に見たわけです。これまで原爆の死というのは、何十万人という「集団としての死」として語られてきた。でも私はたった1人の女の子の死について考えたい、この作品はそこから始まりました。


©Ishiuchi Miyako「ひろしま#71」
このワンピースは、シリーズの一番初めに撮影したものです。見た瞬間に「コム・デ・ギャルソンみたい!」と思いました。後から聞いて驚いたのですが、80年代にコム・デ・ギャルソンの川久保玲が初めてパリコレで発表した洋服は、「原爆ルック」と呼ばれたそうです。遺品たちは小さく畳まれ、紙に包まれて保存されているのですが、私はそれを一番きれいに見える形に整え、最も美しく見えるように撮っています。このワンピースもそうですが、ライトボックスの上にのせて、洋服から身体が透けて見えるかのように撮る。そうすると、私がこの時代に生きていたら、もしかしたらこれを着ていたかもしれないというリアリティーが生まれるんですね。
「ひろしま」を撮り始めてから、私は自分が女性の目で作品を撮っているということをかなり意識するようになりました。というのも、広島も含めて「歴史」とは、結局男たちが作り上げてきたものだと思うんですね。これまで撮られてきた広島の世界も、多くは男性の視点で捉えたものです。本来、視点というのは個人的なもので、男女の差は関係ありません。私自身もこれまで特に自分を女性写真家と考えたことはありませんでした。でもこのシリーズをきっかけに、女性が撮ったということを意図的に言ってもいいかなと思うようになった。今では女性の視点で広島を見つめ、身の丈で広島を捉えた初の試みだと自負しています。
アートで紡ぐ新たなストーリー
石内: この作品を撮るまで、私は広島を訪れたことがありませんでした。私にとって広島は観光地ではなく、行くなら写真を撮りに行くしかない。でもすでにさまざまな人によって撮り尽くされているから、自分があえて撮る必要はないと思っていたんですね。ところが、私の「Mother’s」(自身の母の遺品を撮影した作品集)を見たある編集者がこの撮影を依頼してきたんです。「広島と縁もゆかりもない私がなぜ?」と思いましたが、それが遺品たちと出会うきっかけになりました。
広島の資料館には1万9千点におよぶ遺品が所蔵されていますが、今でも毎年新たなものが届くんです。遺品を持っている方々も徐々に高齢化していて、管理しきれなくなったものが資料館に寄贈されるからです。このシルクのブラウスは、去年の夏に寄贈された一番新しい遺品です。元は白色でした(被爆後変色し、現在はピンク色)。妹さんが手作りして、お姉さまの結婚式に差し上げたものだそうです。
でも実は、そういった話に私は全く興味がないんですね。写真で過去を撮ることはできません。それに私はこれらの遺品を「資料」として撮っているわけではないんです。私にとっては、あくまでも自分が去年の夏に出会ったピンクのブラウスでしかない。強いて言えば、去年の夏、見知らぬ女の子に出会ったという感覚かな。もちろん、写真には記録を残すという運命的な役割があります。でも私の写真は「記録」よりも「創作」に近くて、「私にはこう見えている」ということを表現しています。
広島には絶えず「記録」「反戦・平和」という重いテーマが課せられます。でも私がこれまで手掛けてきた写真は、「記録」から最も遠いところで始めたものばかり。「ひろしま」においてもそうしたキーワードから一切逃れたいと思いました。いかに既存のイメージから離れ、解き放てるか―常にそう考えながら作品を作っています。

美しさに見る歴史の傷跡
石内: 撮影している遺品は被爆した物ですから、傷つき、汚れているんです。でも醜いかと言えば、そうは思いません。美しくなければ、私はシャッターを押せませんから。むしろ私の中には、美しくしてあげたいという意識があって「私には見えているよ、わかっているよ」という気持ちで撮影しています。遺された物たちは語らないけれど、写真を撮ることで、物から聞こえてくる声を伝える力をもらっているように感じます。
遺品がこんなに美しいはずはない、と批判を受けることもあります。でもね、被爆する前はもっときれいだったわけですよ。それに写真をプリントで見れば、原爆の跡が確かに残っている。私の写真にはキャプションが一切ありません。写真の前で「一体これは何だろう」と立ち止まって見てほしいからです。広島は歴史的事件の一つの象徴です。だから私がかかわるときにはそれを情報にしたくない。表現者の姿勢と責任という意味において、何よりも美しさを意識して「ひろしま」を作っています。
今年は戦後70年。「ひろしま」のシリーズも再び注目されていますが、私にとって70年という節目はそれほど関係がありません。戦後はまだ終わっていないんですね。一つの歴史がずっと続いている。今後も資料館に遺品が届く限り、ライフワークとして撮り続けていくつもりです。
「ひろしま」に思うこと
批評家の若松英輔氏は、言葉の人だ。言葉を自在に操り、巧みに物語を語るという意味ではなく、むしろその限界と真摯に向き合い、言葉や実像では語り得ないものの働きを示すことで、多くの人たちの心に寄り添ってきた。その若松氏に、石内氏の「ひろしま」に感じたことをコメントしていただいた。
若松 英輔:初めて石内さんの作品を見た時、私もやはり、あれほど悲惨な出来事があった広島の遺品がなぜこんなにも美しいのかと、何とも整理しがたい気持ちにな り ま し た 。現代人というのは、私を含め、感じたことを解釈したがりますよね。何かを見たら、すぐさまそれに「言葉」を与えたくなる。でも人が交わったり、人間の心と心がふれ合う時、必ずしも言葉は必要ないのかもしれません。むしろ言葉に置き換えることで、実際に起こっていることを小さくしてしまうこともあるからです。私たちの世界には、語り得ないものがあります。でも語り得ないからと言って、存在しないのとは違うんですね。沈黙もまた重要な言葉の働きだからです。
二十世紀日本を代表する哲学者で井筒俊彦という人がいます。彼は「言葉は単層ではない。すべての言葉には深みがある」と言いました。井筒いわく、最も表層にあるのが「リアリスティック」で、現実世界はこの層に当てはまります。2番目の層は「ナラティブ」で、物語や神話を指します。3番目の層は「イマジナル」。これはアンリ・コルバンというフランスのイスラーム神秘主義の哲学者による造語で、現在の世界と他の世界をつなぐという意味です。
私たちは時にリアリスティックな世界でいさかいを起こし、ナラティブな世界で対話を始めます。しかし真の意味での平和は、イマジナルな世界にあると私は思っています。ここで言う平和の定義は、「どうしても許せない人と手を握る」ということ。許してから手を握るのでは、人間は永遠に手を握れないでしょう。ではどうしたら私たちの世界にイマジナルな感覚を持ち込むことができるのか。石内さんの作品を通じて、皆さんと一緒に考えたいと思います。
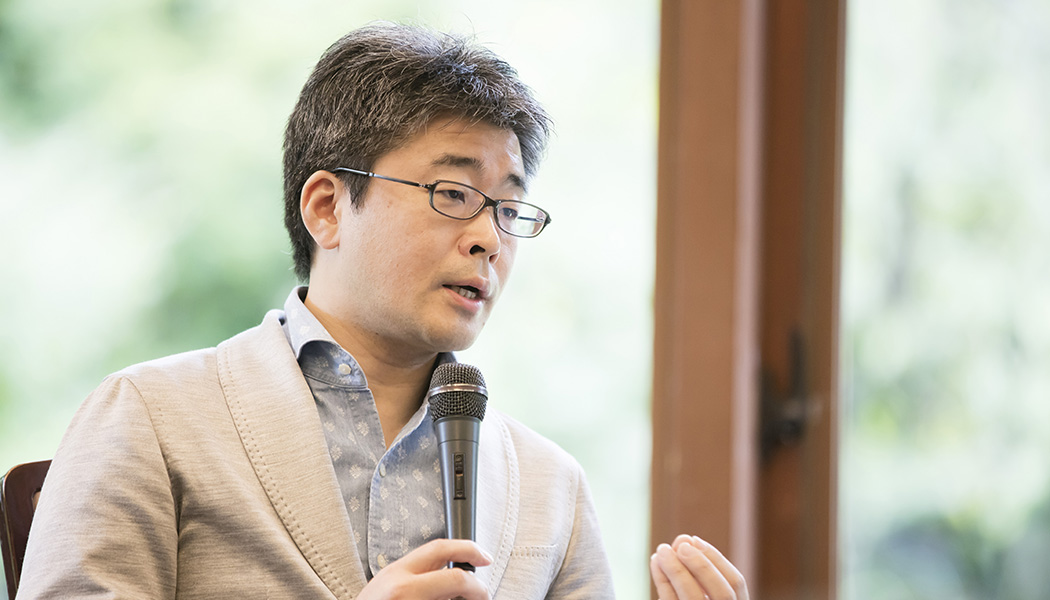
1968年生まれ。季刊文芸誌『三田文学』編集長、読売新聞読書委員。「生きている死者」をテーマにさまざまな執筆、講演活動を行っており、『魂にふれる~大震災と、生きている死者』(トランスビュー、2012年)などの随筆が大きな反響を集める。そのほか『井筒俊彦 叡知の哲学』(慶應義塾大学出版会、2011年)、『生きる哲学』(文藝春秋、2014年)、『霊性の哲学』(角川学芸出版、2015年)など思想家論も多数。
 2015年のALFPフェローは8名。ジャーナリストや環境活動家、詩人、大学教授など専門領域は異なるが、みなアジアの課題を共に考えるために来日した。フィリピンの詩人ディナ・ロマ氏は、言葉の重層性に触れ、「3つの層をすべて内包するものが、まさにアートではないだろうか。石内さんは、遺品というリアルな物と対話することで新たなナラティブを引き出し、それを写真という表現によってイマジナルな世界へと引き上げている。この昇華の過程に存在するものこそがアートであり、それは歴史に新たな視座を与えてくれるのではないか」と語った。<
2015年のALFPフェローは8名。ジャーナリストや環境活動家、詩人、大学教授など専門領域は異なるが、みなアジアの課題を共に考えるために来日した。フィリピンの詩人ディナ・ロマ氏は、言葉の重層性に触れ、「3つの層をすべて内包するものが、まさにアートではないだろうか。石内さんは、遺品というリアルな物と対話することで新たなナラティブを引き出し、それを写真という表現によってイマジナルな世界へと引き上げている。この昇華の過程に存在するものこそがアートであり、それは歴史に新たな視座を与えてくれるのではないか」と語った。<
一方、1983~2009年の民族紛争で多くの人命が失われたスリランカで、平和構築を研究するアルラナンサム・サルベスワラン氏は、「アートにせよ記録にせよ、戦争を伝えることは平和教育に役立つだろう。しかし紛争後間もない地域の場合はどうだろうか?」と問いかけ、和解プロセスの難しさを示唆した。
本セッションでは一橋大学の足羽與志子教授のモデレートのもと、歴史、象徴、暴力、記録、和解など「戦争の記憶」に呼応するさまざまキーワードが引き出された。今後こうした対話が一層深められ、アジアひいては世界の共通課題の解決に資することが期待される。
アジア諸国・地域のさまざまな分野で活躍している専門家たちを、日本に約2カ月間招へいし、日本の専門家との対話などを通じてアジアおよび世界の諸課題を議論しながら、共通の問題意識を醸成し、アジアにおける知的基盤をつくることを目的とするプログラム。国際文化会館と国際交流基金が共同事業として1996年から実施しており、2015年はマレーシア、インド、フィリピン、タイ、スリランカ、中国、インドネシア、日本から8名が参加した。
このセッションは2015年9月10日に行われたものです。
構成・編集:国際文化会館企画部
インタビュー撮影:相川 健一
©2019 International House of Japan
その他のインタビュー・対談記事はこちらへ。
