ナサニエル・ブラウン Nathaniel Brown(映像作家)
2026年6月〜2026年10月
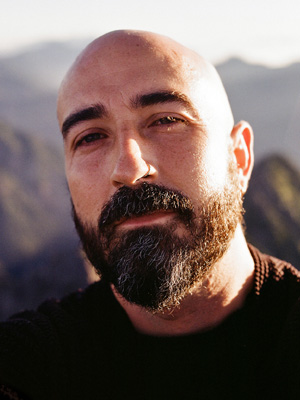
「場所」や「帰属」「コミュニティ」をテーマに制作を行う映像作家・写真家。フルブライト奨学生としての経歴を持ち、ピューリッツァー・センターやメロン財団の支援のもと、作品は『ワシントン・ポスト』『ウォール・ストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』『Vice』『Vogue』『Nowness』『Dazed』『Hypebeast』『Sabukaru』『サウスチャイナ・モーニング・ポスト』などで紹介されている。ドキュメンタリーとフィクションのあわいに位置し、文化的な語りを分散化することに焦点を当てている。これまでDOC NYC、ハワイ、クリーブランド、ビッグスカイなどの映画祭で上映され、撮影賞、ドキュメンタリー賞、観客賞などを受賞している。ミドルベリー大学を優等(Magna Cum Laude)で卒業した後、台北の国立台湾大学および北京の清華大学に留学した。
本フェローシップでは現代の沖縄のアイデンティティと、海との関係の変化を探るハイブリッド・ドキュメンタリーを制作する。アジアや太平洋地域の海洋コミュニティを題材にしたこれまでの活動を踏まえつつ、石垣、宮古島、奄美、沖縄本島に暮らす文化実践者たちとのコラボレーションを通して、沖縄を単純化したイメージで描くことに対する問いを投げかける。
アイザック・イマニュエル&マリナ・フクシマ Isak Immanuel & Marina Fukushima(ダンス・映像作家)
2026年8月〜2027年1月
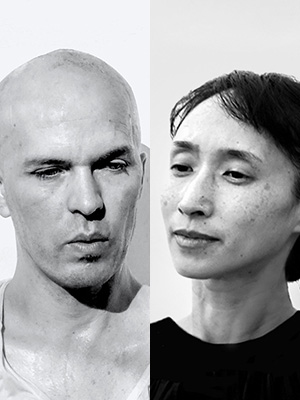
コラボラティブなインターディシプリナリー・ダンス・アーティストユニットとして、「不安定さ」「家」「沈黙」「世代間の関係」といったテーマに取り組む数多くのプロジェクトを制作してきた。2013年以降、体験的なリサーチやサイトスペシフィックなパフォーマンス、映像インスタレーション、そしてコミュニティと関わるソーシャル・アーツの実践を通じて作品を展開している。サンフランシスコ・ベイエリアを拠点にしながら、日本、韓国、台湾、アメリカをはじめ各地での滞在制作を行い、遊動的に活動を続ける。
マリナ・フクシマは東京に生まれ、10代でアメリカに移住した。ダンスを専門とし、バトラー大学でBFA、アイオワ大学でMFAを取得。2005年以降、自身の作品を制作する一方で、KUNST-STOFF、ODC、project agora、Lenora Lee Dance、Tableau Stationsなど、国内外の多くのダンスカンパニーや振付家とコラボレーションしてきた。
アイザック・イマニュエルは、ニューメキシコ州タオスのメサ地帯と、ロサンゼルス東部という対照的な環境で育った。1999年にカリフォルニア芸術大学でインターディシプリナリー・プラクティスのBFAを取得後、アンナ・ハルプリン、カセキユウコ、玉野黄一・弘子、スザンヌ・レイシー、桂勘といった複数のヴィジュアル/ムーブメントアーティストとコラボレーションしてきた。2004年に設立したTableau Stationsの芸術監督として、地域と世界をつなぐ「場所」の問いに取り組む異文化的アートプラットフォームを主宰している。

本フェローシップでは「Landscapes of Youth(若さの風景)」をテーマに、場所に根ざしたリサーチ活動と分野横断的なダンス作品のシリーズを展開する予定。探求の重要な層となるのは、「こども風土記」という概念に基づく、民俗的な風習や、現代における子ども時代の野外での記録である。アーティストとして、子を持つ親として、異なる世代──家族、年長者、若者──、そして日本各地の都市と地方という異なる土地の文脈の中で、いかに耳を傾け、関係を築くことができるかを探る。オーラルヒストリーや野外での感覚的リサーチ、地域の祭りの観察、他のアーティストや親たちとの協働によるサイトスペシフィックな映像・パフォーマンス制作など、社会的実践を重ねるプロセスを通し、土地に根ざした世代間の芸術の実現に向けて、新たな関係性を模索する。
マイケル・ヴェルヌスキー Michael Vernusky(作曲家)
2026年2月〜2026年6月

テキサス州オースティンを拠点に、ライブ・パフォーマンスやラジオ音響作品、オーディオビジュアル体験のための音楽を制作し、その音楽は「大胆不敵」(ニューヨーク・タイムズ)、「孤高的」(The Wire)、「特に異世界的」(New Music USA)と評されている。16年間にわたり、アップル社のエクスペリエンスアナリストとしての仕事とアーティストとしての活動を両立してきたが、現在はフリーランスのメディア作曲家として活動している。
フィールドレコーディストでもあり、北極圏の氷河崩落音から、アマゾンの絶え間ないチェーンソーの音、マラケシュの蛇使いの笛の音までを録音してきた。インドの美しい喧噪から南アフリカの危険なカバの水場まで、世界各地を旅しながら音を集めている。電子楽器と民族楽器、フィールドレコーディング、そして偶然の音を多様なメディア上で融合させ、大規模でしばしば大陸をまたぐ音楽作品を制作し、アルバムとして発表している。これまで、上海音楽学院、イスタンブール工科大学、東京日仏学院、ウィーンのザロン・アルテ・シュミーデ、メキシコの音楽芸術センター(CMMAS)、ハーバード大学、ハダースフィールド大学などで自身の音楽や思想を発表してきた。作品は、BBC Audio、MIT Press、The Wire、NEUS-318(日本)、Ferns Recordings(フランス)、Audiobulb(イギリス)、Quiet Design(テキサス)など多数のレーベルから出版されている。
本フェローシップでは京都と東京を拠点に、尺八や古楽器、フィールドレコーディング、電子音を組み合わせた新作アンサンブル作品の完成に取り組む予定。世代を超えて自らの楽器で現代的な響きを追求する日本の演奏家たちと共演する。
マイカ・ワイルズ Micah Wiles(工芸作家)
2025年10月〜2026年1月

アパラチア山脈のふもと、ケンタッキー州に暮らす農家でありクラフト作家。12年以上にわたりバスケット制作に携わり、この7年間はとくに伝統的なホワイトオーク(白樫)のバスケットづくりに力を入れている。身のまわりの自然から得られる地域の素材を用いる、土地との関わりを重視した制作を行っている。ケンタッキー州やテネシー州の伝統的なバスケットを研究するほか、ルーマニア、アイルランド、イングランド、日本を訪れ、各地の職人から学んできた。知識を受け継ぎ、伝統技術を次世代へとつなぐことを大切にしており、自身の農場や地域のクラフトスクールで様々な教室やワークショップを開いている。
本フェローシップでは日本各地を巡り、籠職人やクラフト作家を訪ね、それぞれの地域に根づく伝統的な籠づくりの技術を学ぶ予定。また、自身の文化に受け継がれる技法やものづくりの伝統を紹介するデモンストレーションやワークショップも行う。
ウー・ハンイェン Wu Hanyen(工芸作家)
2025年10月〜2026年1月

ロードアイランド州プロビデンスを拠点に活動する台湾系アメリカ人のアーティストであり、クラフト作家。木工を基盤とし、人の身体が世界の中をどのように動き、関わるのかという関心を軸に制作を行っている。自身の怪我をきっかけに、身体のケアとクラフトの関係性を探求し始め、日常的に使える動作のためのツール群を生み出すに至った。コミュニティと協働を制作における中心的な要素としており、しばしば他の作り手たちとともに制作し、技術を共有したり、教えたり、共に学ぶ場をつくり出している。ニューヨークで家具製作の職人として5年間働いたのち、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインで家具デザインのMFAを取得。現在はマサチューセッツ芸術大学の立体芸術学科で准教授を務めている。
本フェローシップでは日本各地を巡り、伝統的および現代的な木工技術を学ぶ。旅の途中では、椅子づくり、桶づくり、ナイフづくり、筆づくりのワークショップに参加するほか、各地の工房、学校、美術館を訪れ、地域ごとの職人たちから学び、富山ガラス造形研究所の招聘アーティストとして、自身の家具やオブジェ制作のアプローチを共有する予定。
年度別日米芸術家交換プログラムフェロー
2024|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|2000|1999|1978-1998|
プロフィールTOP | ENGLISH